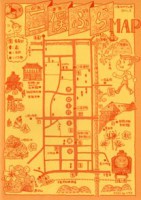和楽器を楽しもう!
静邦会はままつ
琴の演奏や体験を通して、日本の伝統・文化や和楽器に親しんでもらう活動をしています。
はじまりは。。。
学生時代の琴の仲間が浜松に戻って来て、またみんなでやろうと集まったことがきっかけです。
最初に始めたのは、学校に寄贈された琴の状態を調べることでした。市内の小・中学校を訪問して分かったのは、ほとんどの学校で琴が使われずに眠っていて、事務室に置かれたり、校長室に飾られたりして、校内に琴があることすら知られていないという残念な現状だったのです。
そこで、「せっかくの琴をなんとかしたい!」という思いから、学校に出向いて音合わせをしたり、弦を操作したりして、琴を弾ける状態に戻す活動を始めました。次第に演奏の依頼も受けるようになり、学校や公民館、老人ホームなどで、琴や和楽器に興味を持ってもらえるようなプログラムを披露しています。
 思いを引き継いで
思いを引き継いで旧浜松市内の小・中学校にある琴は、市内で琴店を営んでいた故菊岡惣平さんという方が一校に一面ずつ、30年かけてプレゼントしたものです。子どもたちに、琴に親しんでもらいたいという菊岡さんの思いを受けて、子どもたちが琴を身近に感じられるよう伝えていこうと思っています。
こんな思いでやっています
まず何よりも、自分たちの琴が好きという気持ちを大切にしています。そして、日本の文化・伝統である和楽器に興味を持ってもらいたい、もっと知ってほしいという思いが原動力です。
 琴の魅力
琴の魅力琴は一人で弾くのも良いけれど、合奏したり、他の和楽器と合わせたりすることで、とても壮大な表現ができる楽器です。独奏とはまた違った、合奏の深みや楽しさを味わえるのも醍醐味です。
こんな活動をしています
- 1.琴の調整
- 学校を訪問して、音の調整や、弦の操作など、楽器のメンテナンスを行っています。
- 2.演奏・体験活動
- 学校:小中学校や特別支援学級、定時制高校などから依頼を受けて訪問し、和楽器の紹介や演奏、体験を行っています。
 和楽器を紹介することからはじめる
和楽器を紹介することからはじめる演奏・体験活動の一番の目的は、和楽器に興味を持ってもらうこと。
子どもたちに、琴に触れて弾いてみる楽しさを知ってほしいのです。目を輝かせながら、一生懸命取り組んでくれる姿は、自分たちの励みにもなります。
- 公民館・老人ホーム:公民館まつりなどのイベントに出演したり、老人ホームでの演奏を行っています。尺八と一緒に演奏したり、子どもからお年寄りまでみんなが知っている曲を選んだりして、楽しく過ごしてもらう工夫をしています。
- 3.定期練習
- 毎月第2日曜日に、県居公民館で演奏の準備や練習を行っています。
 豊富なレパートリー
豊富なレパートリー琴はどんな音階の曲にも対応できる、自由自在な楽器なのです。
静邦会はままつでは、古典から現代曲、そして懐メロまで取り組んでいます。
箏曲らしい「さくら」や「六段」だけでなく、わらべ歌や「山寺の和尚さん」などみんなが知っている曲、「さんぽ」や「千の風になって」、「崖の上のポニョ」、「千と千尋の神隠し」は一緒に歌える曲、「東京進行曲」、「影を慕いて」、「東京音頭」など懐かしい曲を演奏しています。
参加するには。。。
- 練習・演奏会に参加する
- 琴を弾くのが好きな人、琴を弾いてみたい人など、一緒に演奏活動をする仲間を募集しています。
- 演奏や体験を依頼する
- 琴の演奏や、体験会の依頼を受け付けています。(日にち、場所、目的、曲目によって要相談)
こんな団体です
- 活動分野
- 文化・学術、人権、和楽器紹介
- 活動対象
- すべての人
- 活動地域
- 浜松市内
- 設立年
- 1994年
- 会員
- 15人
- 会費
- 2,000円/年、入会金なし
- 運営スタッフ
- 5名
- 代表者名
- 鈴木 順子(すずき じゅんこ)
- 連絡先
- (住所)〒430-0926 浜松市中央区砂山町339-26
(電話)053-453-8530




 ブラジル人学校、日本の幼児、小・中学校からブラジル人、日本人やその他の国籍の子ども、教員、保護者、地域の大人などが参加しました。ブラジル人学校の子どもや先生たちは、普段他校の生徒や先生と交流できる場が少なく、運動会で一同に会したのはとても良い機会となりました。
ブラジル人学校、日本の幼児、小・中学校からブラジル人、日本人やその他の国籍の子ども、教員、保護者、地域の大人などが参加しました。ブラジル人学校の子どもや先生たちは、普段他校の生徒や先生と交流できる場が少なく、運動会で一同に会したのはとても良い機会となりました。
 浜松市の青少年課が「青少年の健全育成」の事業として、浜松に集団就職してきた子どもを対象にはじめた通信制高校の学習会が前身です。
浜松市の青少年課が「青少年の健全育成」の事業として、浜松に集団就職してきた子どもを対象にはじめた通信制高校の学習会が前身です。




 引佐町の田畑地区には数多くの棚田跡が存在し、そのほとんどが昭和30~40年代の高度成長期に耕作放棄された棚田でした。「ある時、木漏れ日の中で、累々と積み上げられた棚田の石組を見たときにね。感動したんですよ。地域の宝物に見えた。」それがきっかけとなり、地域の絆の証である棚田を復元し助け合いの気持ちを追体験しようと有志が集まって発足しました。
引佐町の田畑地区には数多くの棚田跡が存在し、そのほとんどが昭和30~40年代の高度成長期に耕作放棄された棚田でした。「ある時、木漏れ日の中で、累々と積み上げられた棚田の石組を見たときにね。感動したんですよ。地域の宝物に見えた。」それがきっかけとなり、地域の絆の証である棚田を復元し助け合いの気持ちを追体験しようと有志が集まって発足しました。
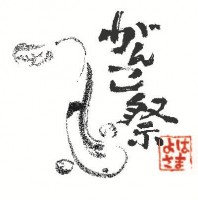



 代表が開催しているカラ―教室の生徒の声をきっかけに活動が始まりました。当時街中に周りの景観とは極端に違う色彩の店舗が建ち、「違和感」「騒色」が話題になり、色彩の知識で街中の美観について測色調査を行い、その結果を基にフォーラムを開催して活動の輪が広がっていきました。
代表が開催しているカラ―教室の生徒の声をきっかけに活動が始まりました。当時街中に周りの景観とは極端に違う色彩の店舗が建ち、「違和感」「騒色」が話題になり、色彩の知識で街中の美観について測色調査を行い、その結果を基にフォーラムを開催して活動の輪が広がっていきました。